
前回の記事はコチラ!
第34回 教えて!リス太くん

前回の続きだよ!
「睡眠12箇条」でからだもこころも健康になろう~
1.良い睡眠で、からだもこころも健康に
睡眠の役割についての情報です。睡眠は生物にとって必要な生理現象です。
しっかり眠らなければ心身の疲労は回復されません。
睡眠が量的に不足したり、質的に悪化したりすると健康上の問題や生活への支障が生じ生活習慣病のリスクにつながることがわかってきています。
実際に睡眠の質が悪いと、血圧が上昇し、脳梗塞や心筋梗塞などのリスクが上がることが指摘されています。不眠とうつ病は有意に関係し不眠が続けばうつ病発症のリスクも上昇し心の病に関係すると言われています。
睡眠不足や睡眠障害による日中の眠気がヒューマンエラーに基づく事故や交通事故などの重大な事故を起こしてしまった例もあるそうです。
「睡眠は心身の健康の基本」ということを忘れず、良い睡眠をとれるように心がけてください。

2.規則正しい食生活と定期的な運動が大切
- 定期的な適度な運動を習慣づけ規則正しい食生活は良い睡眠をもたらします。
- 朝食をとることは朝の目覚めを促します。
朝食は、栄養補給という意味の他、「これから一日が始まる」と身体に認識させる作業でもあります。
朝食をとることで、胃腸が動き出して全身にエネルギーが回り、「これから活動するぞ」と身体が活動モードに切り替わります。 - 良質な睡眠を得るために、適度な運動は必須です。身体は動かさなければ疲れません。そして、疲れなければ眠れません。良質な睡眠を得るためには適度な運動は欠かせません。特にデスクワークの方は、脳は酷使するけど身体は使わないことが多い為に脳は疲労しているけど、身体は疲れていない・・・・脳は睡眠を欲するけども、身体は別に欲していないアンバランスから睡眠の質が悪くなります。睡眠の質を上げるために、脳と身体をバランス良く疲れさせることは重要なことです。通勤をなるべく歩いてみるとか、なるべく階段を使うとか、小さな工夫でも構いません。
3.良い睡眠は、生活習慣病予防につながります
- 睡眠薬代わりの寝酒は寝付きを良くしますが、眠りを浅くしてしまうので睡眠の質は低下します。
- 就寝前の喫煙やカフェイン摂取を避ける。就寝前3~4 時間以内のカフェイン摂取は、入眠を妨げ睡眠を浅くする可能性があります。生活習慣によって、睡眠と覚醒のリズムにメリハリをつけることができます。

4.睡眠不足と生活習慣病には密接な関係が
睡眠時間が不足している人や不眠がある人では、生活習慣病になるリスクが高いことが わかってきています。
睡眠不足や不眠を解決することで、生活習慣病の発症を予防できます。
放置すれば高血圧や糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞などのリスクを高めます。
肥満は生活習慣病の原因になるだけでなく、睡眠時無呼吸症候群の原因にもなり、睡眠の質を悪化させます。
睡眠時無呼吸は過体重や肥満によって、睡眠時に気道(喉の空気の通り道)が詰まりやすくなることで発症、重症化します。
睡眠時無呼吸症候群は治療しないでおくと高血圧、糖尿病、ひいては不整脈、脳卒中、虚血性心疾患、歯周疾患などのリスクを高めます。
予防のためには、肥満にならないことが大切です。
良質な睡眠を取るということは、生活習慣病から身を守るということにもなるのです。
5.こころの健康を保つために睡眠による休養を
寝つけない、熟睡感がない、早朝に目が覚めてしまう…。
疲れているのに眠れないなど不眠症状は、こころの病のSOSとして現れることがあります。
うつ病になると9 割近くの人が何らかの不眠症状を伴うといわれます。
逆に不眠のある人はうつ病にかかりやすいことも知られています。
うつ病に限らず睡眠時間が不足していたり、不眠症のため寝床に就いても眠れなかったりして、睡眠による休養感が得られなくなると、日中の注意力や集中力の低下、頭痛やその他のからだの痛みや消化器系の不調などが現れ、意欲が低下することが分かっています。
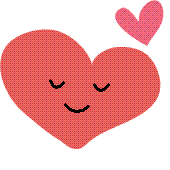
6.年齢や季節に応じて適正な睡眠時間を
昔から、『年をとると早寝早起きなり若いときのように長時間眠れない』といわれます。
睡眠量は、年を取ると徐々に減っていくのが普通です。高齢者の方であれば、若い時と同じ睡眠を求めず、個人差はあるものの、成人の平均的な睡眠時間は6 時間以上8 時間未満が標準的なようですが、あくまでも平均に過ぎません。
人それぞれ、自分に最適な睡眠時間は異なりますので、「〇時間、睡眠をとらなくてはいけない」と考えるにではなく自分に合った最適な睡眠時間を探して下さい。
一般的に日照時間の長い夏では睡眠時間は短くなり、日照時間の短い冬では睡眠時間は長くなります。
同じ人でも季節によって多少、最適な睡眠時間は異なります。
睡眠時間と生活習慣病やうつ病との関係などから言えますが、必要な睡眠時間以上に長く睡眠をとったからといって、健康になるわけではありません。
必要な睡眠時間は人それぞれということですね。
日中の眠気で困らない程度の自然な睡眠が一番です。
特に、「〇時間眠ろう」と時間で自分の睡眠を評価することは好ましくありません。
一般的には短いと言われている睡眠時間でも、日中に問題なく活動できるのであれば十分です。

7.自分の睡眠に適した環境づくり
良い睡眠のためには、自分の睡眠に適した環境づくりも重要です。

温度や湿度は季節に応じて眠りを邪魔しないと範囲に保つことが基本で、心地良いと感じられる程度に調整しましょう。だいたい25~29℃前後が適温。
明るい光には目を覚ます作用があります。
室の照明が明るすぎないか、外から光は入ってこないか。
騒音がひどすぎることはないか。
就寝時には、必ずしも真っ暗にする必要はありませんが、自分が不安を感じない程度の暗さに、自分にあったリラックス法が眠りへの心身の準備となる。
睡眠の質を上げるためには、睡眠に適した環境を意識することも大切です。
ゆっくり入浴したり、寝る前にストレッチをしたりなど、自分に合ったリラックス法を用いることで睡眠の質を高められます。
8.若年世代は夜更かしを避けましょう
若年世代では、夜更かしが頻繁に行われることで体内時計がずれてしまい、睡眠時間帯の不規則化や夜型化を招くリスクがあります。
寝床に入ってから携帯電話、メールやゲームなどに熱中すると目が覚めてしまい、さらに就床後に長時間、光の刺激が入ることで覚醒が助長されます。
休日に遅くまで寝床で過ごすと夜型化を促進
体内時計のリズムを整えるには、朝日を浴びることが効果的です。
朝日には体内時計をリセットするはたらきがあるからです。
9.睡眠で疲労回復・能率アップを
睡眠不足が長く続くと疲労回復は難しくなります。
睡眠不足による疲労の蓄積を防ぐためには、毎日必要な睡眠時間を確保することが大切です。
睡眠不足は注意力や作業能率を低下させ、生産性を下げ、事故やヒューマンエラーの危険性を高めます。
毎日十分な睡眠をとることが基本ですが、仕事や生活上の都合で、夜間に必要な睡眠時間を確保できなかった場合、午後の眠気による仕事の問題を改善するのに昼寝が役に立ちます。
午後の早い時刻に30 分以内の短い昼寝をすることが、眠気による作業能率の改善に効果的です。
不眠症の予防や早期発見のためには、日中の眠気がないかをチェックしましょう。
日中の眠気は睡眠不足のサインであり、これが認められる場合は睡眠時間を増やすか、日中に昼寝などの仮眠を取ることで睡眠量を適正にする必要があります。
寝不足を休日の「寝だめ」で対応しようとする方がいますが、実は睡眠は溜められるものではありません。つまり寝だめは意味がないのです。
睡眠不足を放置しておけば、仕事のミスも増えます。
また一度不眠症を発症してしまうと、治すまでに時間がかかるため早めに予防することが大切です。
10.熟睡の工夫が大切
健康に資する睡眠時間や睡眠パターンは、年齢によって大きく異なります。
高齢になると、若年期と比べて必要な睡眠時間が1時間短くなると言われるので、寝床で長く過ごしすぎる夜中に目覚めやすくなり熟睡感が減ってしまいます。
日中に適度な運動を行うことで、昼間の覚醒の度合いを維持・向上し、睡眠と覚醒のリズムにメリハリをつけ中途覚醒が減り睡眠を安定させ、質の良い睡眠を得ることが出来ます。
11.眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない

眠たくなってから寝床に就く、就床時刻にこだわりすぎない。
眠たくないのに無理に眠ろうとすると、かえって緊張を高め、眠りへの移行を妨げます。
自分にあった方法で心身ともにリラックスして、眠たくなってから寝床に就くようにすることが重要です。
まだ眠くないのであれば、眠くなるまで起きていましょう。
眠ろうとする意気込みが頭を冴えさせ寝つきを悪くする
「寝なくては!」という意気込みからかえって寝付けなくなります。
また身体を横にしてしまうことで疲労が起こらず、睡眠の質も低下します。
眠れないときは、いったん寝床を出て、リラックスできる音楽などで気分転換し、眠気を覚えてから再度寝床に就くようにすると良いでしょう。
眠りが浅いときは、むしろ積極的に遅寝・早起きに
寝床に入る時刻が遅れても、朝起きる時刻は遅らせず、できるだけ一定に保つことが大切です。
朝の一定時刻に起床し、太陽光を取り入れることで、入眠時刻は徐々に安定していきます。
12.いつもと違う睡眠には、要注意。 睡眠中の身体の異変に要注意
睡眠中の激しいいびき・呼吸停止、手足のぴくつき・むずむず感や歯ぎしりは要注意
睡眠中の心身の変化には、専門的な治療を要する病気が隠れていることがあるため、注意が必要です。
激しいいびきや呼吸停止が出る睡眠時無呼吸症候群を適切な治療で改善することにより、高血圧や脳卒中の危険性を減らします。
就寝時の足のむずむず感や熱感はレストレスレッグス症候群、睡眠中の手足のぴくつきは周期性四肢運動障害の可能性があります。
睡眠中の歯ぎしりがある人は顎関節の異常や頭痛を持つことが多いことが示されています。
いずれも医師や歯科医師に早めに相談することが大切です。
眠っても日中の眠気や居眠りで困っている場合は、専門家に相談してみてください。
まずは気軽に相談してみてくださいね!メールフォーム・LINE・電話のどれでも対応してます!



