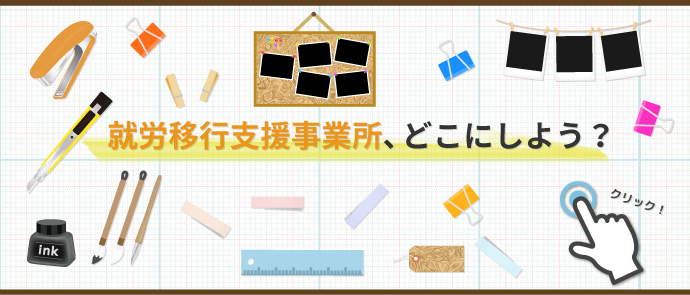「何のために働くの?」があいまいな時、考えてみたいこと
「仕事をする目的」曖昧になっていませんか?
- 「働く」と決めたときにはあったはずの情熱が・・・
- あれこれ指示が右往左往、会社の方針がわからない・・・

仕事をする理由①
リス太君は、明日の会議に出席するようです。
このように、依頼された仕事をただこなすだけでは、目的意識がなく、物足りなく感じるでしょう。
会議の目的は?
このように、自分が資料作成を依頼された背景をどんどんさかのぼって考えてみましょう。
行きつく先は、経営理念のはずです。
「この会社は○○という点で社会に貢献する」
「わが社は○○でお客様を幸せにする」
といった目標を達成するために、日々会社では仕事が進んでいるのではないでしょうか。
意思決定や判断の際の軸にもなる
経営理念は、重要な判断の軸にもなります。
海外支店などを考えてみましょう。
時差もあり、日本にある本社の代表からの指示は待てません。
こういった場合には経営理念が、意思決定の軸になることがあるのです。
仕事をする理由②
先ほどのように、資料作成を頼まれた場合を考えてみましょう。
その資料作成、自分はなぜ請け負ったのでしょうか。
会社のため、というのもひとつありますが、もう少し踏み込んで考えてみてください。
「自分のスキルをあげたいから」
「人の役に立ちたいから」
「お客様に喜んでもらいたいから」
働く、と決めたとき、自分の中にはどのような目標があったでしょうか。
この目標や、自分の人生の判断基準は、どういったものでしょうか。
「ほめられたいから」
といったこともあるかもしれません。
今一度、自己分析をしてみることもよい手段でしょう。
自分の意思決定の軸と、会社理念とのつながり
会社理念ばかりあっても、自分の意思だけがあっても、どちらも成り立ちません。
会社理念は、メンバーの意思が、理念とつながるところがあるから生きるものです。
「最新技術を通して社会貢献する」という経営理念は、「最新技術を身に着けたい」「お客様の役に立ちたい」という個人の思いがあれば、実現にさらに近づきます。
経営理念と自分の意思があまりにも遠いところにある、と言った場合は、なかなか考えられませんが、もしそうであった場合、自分で方向転換をする必要があるのでしょう。