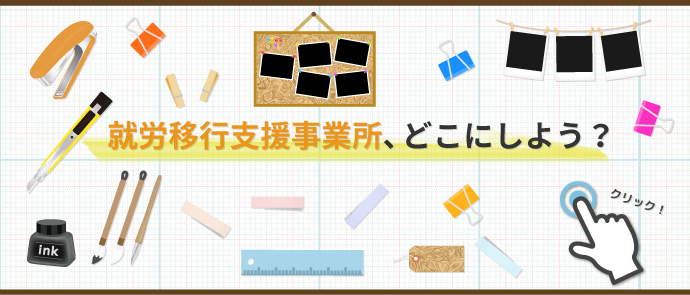選択理論の復習② 外的コントロールによるコミュニケーションの問題点
就労移行支援事業所 リスタート のSSTの中で、「選択理論」という考え方を紹介しています。
前回から、選択理論の考え方について、復習をしています。
今回は、外的コントロールによるコミュニケーションにはどのような問題があるのか、説明していきます

外的コントロールの問題点
前回の記事で、外的コントロールを使ったコミュニケーションと内的コントロールを使ったコミュニケーションでは、人間関係に大きな差異が出てくるとお伝えしました。
この違いを知るのにぴったりなのが、「ハートビーイング」というワークです。
これは、ハートの外に「使われて嫌な言葉、行動、態度」を、ハートの中に「使われて嬉しい言葉、行動、態度」を書き入れるというワークです。
このワークをすると、「うるさい!」「○○さんはできるのになんであなたはできないの?」などといった言葉がハートの外側に出てきます。
実は、これらの言葉は外的コントロールに基づいています。
相手を静かな状態に”変えようと”したり、できていないことをできる状態に”変えようと”している、というわけですね。
また、舌打ちや暴言といった行動もハートの外側に出てくると思いますが、これらも外的コントロールに基づいていると言えます。
なぜなら、こういった行動には、「誰かが悪いことをしたからやった」という考えが潜んでいるからです。
内的コントロールで考えれば、行動は自分で「選んで」行うものであり、「あいつがぶつかってきたから舌打ちした」というのは外的コントロールの考え方なのです。
一方、ハートの内側に書かれるのはどのような言葉、行動でしょうか。
「ありがとう」「お先にどうぞ」などの配慮を示す言葉や、「ちゃんと話を聞く」「励ます」といった、相手を尊重する行動などが出てくるかと思います。
こういった、相手を尊重することや、配慮を示すことは、「人は自分の選択によってのみ行動を決める」という内的コントロールに基づいた行動であると言えます。
このように、外的コントロールに基づいた言動は、相手に苦手意識や悪感情を持たれやすくなってしまうのです。
致命的な7つの習慣と身に着けたい7つの習慣
選択理論を提唱したウイリアム・グラッサー博士以下の言動を差して典型的な外的コントロールと内的コントロールそれぞれの行動であるとしました。
致命的な7つの習慣
①批判する
②責める
③文句を言う
④ガミガミ言う
⑤脅す
⑥罰する
⑦目先の褒美で釣る
身に着けたい7つの習慣
①傾聴する
②支援する
③励ます
④尊敬する
⑤信頼する
⑥受容する
⑦意見の違いを交渉する
外的コントロールを使う頻度を減らし、内的コントロールを使う頻度を増やしていくだけでも周囲との関係は改善していくはずです。
外的コントロールを使ってしまう人の2つの傾向
外的コントロールでコミュニケーションを行ってしまいやすい人の、2種類の傾向があります。
まず1つは、正義感や責任感の強い人です。
間違っていることを正さなければいけない、ちゃんと結果が出るようにしなければいけないと考えた結果、他者を強引に変えようと、外的コントロールで行動してしまうというパターンですね。
例えば、「勉強しないのならゲームは禁止!」と子供に叱る親や、部下のミスを他の社員たちの前で叱りつけてしまう上司などが当てはまるでしょうか。
そして、こういった人が外的コントロールに基づいて行動してしまうのは多くの場合、「自分もそうされて頑張ってきた」という意識があるためです。
実際には、外的コントロールを使うことによって人間関係がうまくいかなくなることも多々あるものの、「自分もそうだったから」「こうするのが当然なのだ」という考えから抜け出すことができなくなってしまうのです。
もう1つは、自分の欲求を満たすため、というケースです。
例えば、自分に自信がなく、「一番の成績を取っていなければ存在価値がなくなってしまう」と考えている上司が、良い成績を収めている部下の細かなミスを探し、怒鳴りつける、といった場面が見られることがあります。
「相手を変えるため、成長させるため」だった先ほどの例とは異なり、「追い抜かれて自分の存在価値を失うのが怖い」という気持ちがベースになっていると考えられます。
このようにして、相手を批判したり、罰を与えることそのものが目的となり、外的コントロールを使ってしまっていることもあるのです。