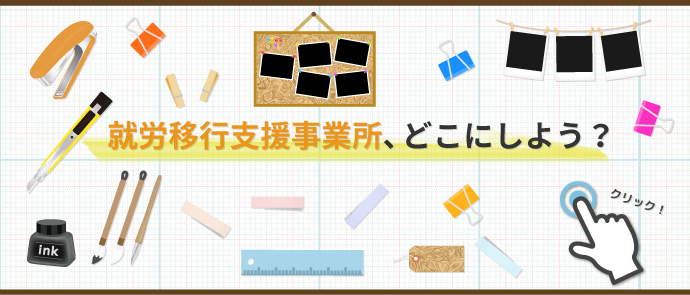ワークショップ「小学生に必要なのは「理科」か「社会」か」/自己分析「メタ認知で自分を分析する」
ワークショップ「小学生に必要なのは「理科」か「社会」か」

ワークショップは、意見に対して質問をすることにクローズアップした訓練になっています。
発表者の発表に対して他の利用者さんが質問をし、それに回答していくことで、意見を作るときに欠けていた視点を見つけたり、改善点を見つけていくことができます。
また、質問を考えながら他の人の発表を聴くこと自体も、話を聞くことや疑問点を確認することの練習になりますよ。
今回のテーマは「小学生に必要なのは「理科」か「社会」か」です。
小学3年生から授業が始まる「理科」と「社会」。
もしも、この2つのうち、より必要なのはどちらかを決めなければいけないとすれば、どちらを選ぶでしょうか。
それぞれを学ぶ意味から、利用者さんに考えてみてもらいました。
このテーマについての利用者さんの意見
- 理科。起きる現象とその解明は世界で共通のものであり、拡張性があるため。
- 社会。身近なことを幅広く学ぶことができるため。
- 社会。小学生で学ぶ理科は身の回りで起こることなので、自分で調べることもできるが、社会は身近なこと以外も知ることができるため。
- 社会。日本や海外の社会の動向を知ることは、生きていく上での自分の生活と密接にかかわりあっているから。
理科と社会、どちらも重要な教科ではありますが、そこで学ぶ内容は大きく違いますよね。
どちらが重要か考えてみることで、それぞれの物事の考え方や、重要視することが見えてきました。
自己分析講座

前回は、「思考」や「行動」についての自分の特徴を考え、まとめてもらいました。
今回は、自分自身のことを客観視する「メタ認知」について紹介します。
メタ認知で自分を分析する
メタ認知というのは、「自分が考えていることを、考える」ということです。
ゲームが好きな人には、「画面の中の自分のキャラクターを見ている、画面の外の自分自身」といったイメージがわかりやすいかもしれません。
自分の思考を客観的に見るメタ認知は、感情に振り回されずに自分の思考を冷静に観察するのに役立ちます。
「どうして自分がそう考えているのか」に目を向けることで、自分を苦しめている考え方に対して対抗することができるようになるのです。
メタ認知を実践するための単純な方法は、自分が思っていることや考えていることを書き出し、その前後に、「今、私は」「と考えている」という文を書き足してみることです。
さらに、可能であればそこに、自分が感じている感情も付け足してみてください。
例えば、
「今、私は」「お腹が空いたなあ」「と考えている」
「今、私は」「話している相手の感じが悪い」「と考え、イライラしている」
「今、私は」「自分はダメ人間だ」「と考え、落ち込んでいる」
といった具合です。
自分がどう考えているのかを客観的に見ることができたら、その考えに「なぜ?」と問いかけていくことで、自分の根本にある考えを探すことができます。