適応障害とは?②~適応障害の特徴~

前回の記事はコチラ
第94回 教えて!リス太くん
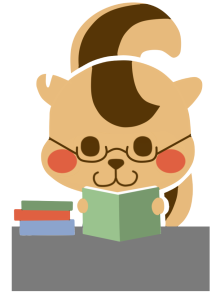
今日は適応障害の特徴について!
さらに詳しく見て行くよ~
私たちの健康は、交感神経と副交感神経という二つの自律神経のバランスによって保たれています。
自律神経は全身の器官をコントロールしているため、バランスが乱れると
体中の色々な部分に支障が出ます。
適応障害ってどんな病気?
適応障害とは、ストレスが起因となって精神的な情緒面、及び行動面の症状として
社会に適応する力が弱まり、社会適応力が障害されている状態にあることをいいます。
夫婦の不和や教育、過重労働、部署異動、結婚、離婚など、良い出来事、悪い出来事問わず
生活が変化することによってストレスを感じ、そのストレスに適応できずに生じる心の症状です。
『ある環境』と『自分の価値観のズレ』が大きく、
その環境に適応しようと努力しても適応できない事によって起因する過剰反応を適応障害といいます
人には1人1人個人差があり、同じ環境でも感じ方はそれぞれ違うので
受けるストレスの影響度や適応力は人により違いがあります。
環境が変化してもとくに問題なく適応できる人もいますが、
同じ環境の変化でもそれを苦痛と感じて、健康的な社会生活ができなくなってしまう人もいます。
「適応障害」とはストレスに対して、頑張りに頑張った結果生じてしまうものなのです。
ストレスとなる状況や出来事がはっきりしているので、
その原因から離れると、症状は次第に改善します。
健康な状態と病気の状態の境目に生じる症状ともいうことができます。
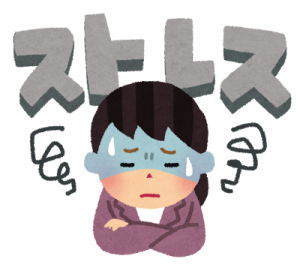
適応障害の診断
適応障害の診断は、除外診断であるという点でほかの精神疾患と趣が異なります。
そのため、統合失調症、うつ病などの気分障害や不安障害などの
診断基準を満たす場合はそちらの診断が優先されることになります。
適応障害と診断されるのは、次の要素を満たす時です。
・日常生活や仕事に支障をきたすほど症状が強い
・環境変化によるストレスが原因であり、その原因が特定できる
・環境変化から3ヶ月以内に症状が発現している
・原因ストレスから離れれば、速やかに症状が改善する
・他の病気(精神疾患)の所見が見られない
適応障害は、日常的範囲のストレス症状が出た後、1~3か月という比較的短期間で、
・精神症状(うつ、不安、イライラ、焦燥、怒り、混乱)
・身体症状(不定愁訴、睡眠障害、食欲低下、易疲労感、倦怠感、痛み、下痢)
・問題行動(遅刻、欠勤、飲酒、夫婦不和、乱費、ギャンブル、自傷行為)
などが顕著に出現し学業や仕事などの社会的機能が障害を受けます。

ICD-10の診断ガイドラインを見ると、
「発症は通常生活の変化やストレス性の出来事が生じて1カ月以内であり、ストレスが終結してから6カ月以上症状が持続することはない」
とされています。
また、適応障害ははっきりと特定できるストレスが原因になっています。
日常的ストレスとの因果関係がはっきりしていているので、
ストレス因から離れると症状が改善することが多くみられます。
たとえば仕事上の問題がストレス因となっている場合、勤務する日は憂うつで不安も強く、
緊張して手が震えたり、めまいがしたり、汗をかいたりするかもしれませんが、
休みの日には憂うつ気分も少し楽になったり、趣味を楽しむことができる場合もあります。
うつ病となるとそうはいかないことがあります。
環境が変わっても気分は晴れず、持続的に憂うつ気分は続き、何も楽しめなくなります。
これが適応障害とうつ病の違いです。
持続的な憂うつ気分、興味・関心の喪失や食欲が低下したり、
不眠などが2週間以上続く場合は、うつ病と診断される可能性が高いでしょう。
「学校に行けない」「無気力」などの症状があらわわられ、社会生活に影響します。
また、これと決まった症状が存在しないというのも適応障害の特徴と言えます。




“適応障害とは?②~適応障害の特徴~” に対して2件のコメントがあります。