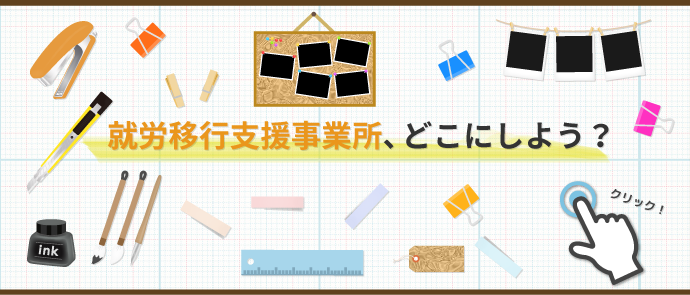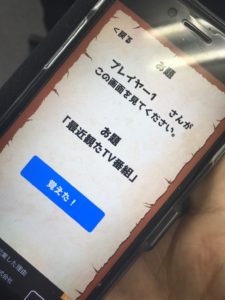認知行動療法講座「5つのコラムの練習②」/ 就活対策「立ち居振る舞い」
新聞読解「AI政治がやって来る 改革の手段となるか」

以下、記事の要約です。
好むと好まざるとにかかわらず人工知能の時代がやって来る。
いちばん縁遠いと思われている政治の世界も決して例外ではない。
政治にもAIなどの科学技術を活用する「ポリテック」。
政策立案から立法、選挙まで、すでにさまざまな動きが出始めている。
ことしは4月の統一地方選、7月の参院選と政界に新しい人材が入ってくる年。
AIを理解し使える政治家が出てくれば、政策の決め方がかわり政治の見える化がすすめで「AI政治改革」につながる可能性をひめている。
この記事に対する利用者さんの意見・感想
- まずは投票率を上げるのが先だと思った。
- AIの導入は賛成だが政策立案をAIに任せるのは心配だ。
- AI導入は政治家の多くが反対しそう。
- AIがいつ人間に敵対心を持つか分からない。
AIに頼らず今一度政治の在り方を見直す必要がありそうですね!
認知行動療法講座
就労移行支援事業所リスタートでは、「ものの受け取り方(認知)」を変えることで「感情」やそれによる影響を抑える「認知行動療法」についての講座を毎週やっています。
今回も、「5つのコラム」の練習を続けていきます。
5つのコラムの練習
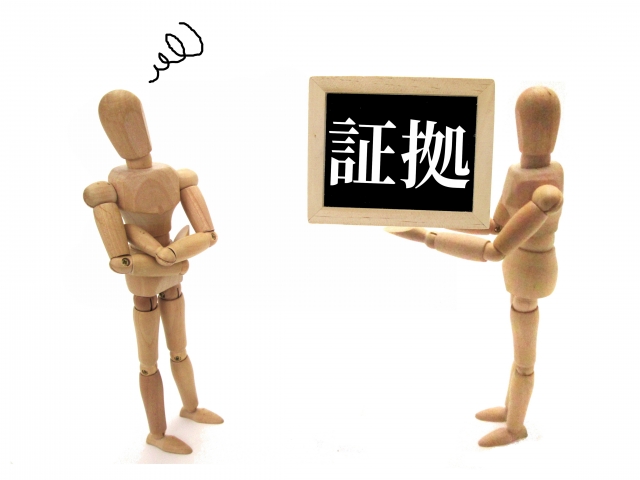
第4のコラム「根拠」と第5のコラム「反証」・・・だんだんとわかってきましたでしょうか。
「根拠」は、その自動思考が浮かんだ原因となる出来事について考えると見つけやすいと思います。
もしも、自動思考が浮かんだ原因に、「事実」と言い切れるものがなければ、根拠のない考えであるとして、それ自体を反証としてください。
「根拠」に対して、「反証」のほうが見つけることが難しく感じるかもしれません。
自動思考と矛盾する事実は、中々見えてこなかったり、見えていても認められずに、無意識のうちに除外してしまっていることがあります。
そこで、事前にチェックした「認知の歪み」が役に立ちます。
例えば、「心のフィルター」や「マイナス化思考」が含まれている考えであったなら、自分を取り巻く状況を見返すことで、自動思考に含まれていなかった事実が見えてくるかもしれません。
「白黒思考」や「べき思考」が含まれていたのなら、「これしかない」と考えていたことが、実は視野を狭めた考え方であったことに気づくかもしれません。
「反証」に気づくために有効な方法は他にもあります。
他の人が自分と同じ考え方をしていたらどのように助言するか、親しい人が同じ状況にあったら、その人はどのように考えるかを想像してみてください。
認知の歪みが出てしまっているときは、自分自身に対して、過剰に厳しく、責めるような考え方をしてしまっている場合があります。
そこで、他者であればどうか、という視点で考えてみることにより、適応的な思考を導き出しやすくなるのです。
就活対策『立ち居振る舞い』

リスタートの就活対策講座は、ビジネスマナーについてただ講義を聞く形式ではなく、利用者さん自らで調べ、発表するという形式で進めています。
ただ講義を聞くだけよりも記憶に残りやすいだけでなく、「情報を収集する力」や「他人に伝える力」を磨くことができます。
前回まではグループに分かれてやっていましたが、今回は「立ち居振る舞い」に関することを、個々で調べて発表してもらいました。
今日のポイントは、『社内の歩き方』、『話を聞く姿勢』の2点です!
発表
今回は、このような内容について発表していただけました!
社内の歩き方
- 人がいなくても端のほうを歩くよう心がける。中央はお客様が歩くところ。
- 横いっぱいに広がらず一列で。お客様がいる場合はやや前を、上司がいる場合はやや後方を歩く。
- 通路は走らない。急いでいても早歩き程度にとどめる。
- お客様や上司とすれ違う際は、通路を譲り、挨拶・目礼をする。
背中を丸めたり下を向いたりして歩いていると、自信ややる気がなさそうに見えてしまいます。
また、ポケットに手を入れたまま歩いたり、蟹股になったり、靴をひきずったり。。。だらだらした印象の歩き方はいけませんね。
目線はまっすぐ、背を伸ばして姿勢よく。きびきび歩いていきましょう!
話を聞く姿勢
- 背筋を伸ばし、顔を上げる。座っている場合は深めに腰を掛け、男性なら膝を開きすぎないように座る。女性なら膝を合わせてかかともそろえます。
- 脚や腕を組んだり、ふんぞりかえったりしない。
- 相手に注目し、うなずき・相槌をうつ。
- 途中で話をさえぎらない。質問は話が終わったらまとめて行う。
- 作業中の手を止めて聞く。
メモをとりながら、また相槌やうなずきを入れて、話を聞いている・聞く意思があるということを伝えましょう。
腕や足を組んだり、体を揺らしたりしながら話を聞くのはマナー違反ですね。