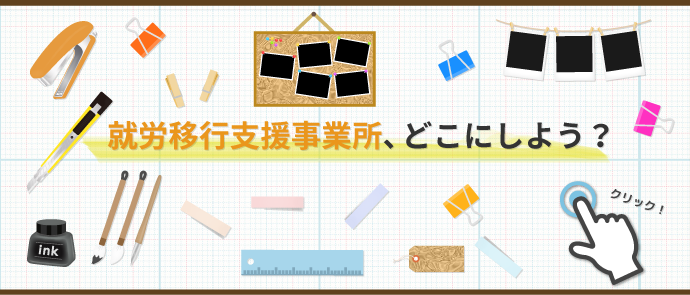認知行動療法講座「7つのコラム」/ 就活対策 「PREP法/電話対応~取り次ぎ~」
目次
新聞読解「ポイント還元 浸透鈍く」

以下、記事の要約です。
消費税を8%から10%に引き上げる10月1日まであとあと1か月。5年半ぶりの増税を点検する。8月上旬、宇都宮で商工会議所が開いたセミナーは約100席の会場が経営者らで埋めつくされた。テーマはポイント還元事業。主催者の男性は「想定の倍の申し込みがあり、大きな会場に切り替えた」と話す。
この記事に対する利用者さんの意見・感想
- ポイント還元で相殺しているだけにも感じる。
- 還元率だけでなくレジのスムーズさや使いやすさも考えてほしい。
- 政府の補助金だけだと一時的な対策になってしまうのではないか。
- キャッシュレス決済など複雑になっていてまだ普及していないと思う。
消費税が10月で10%になることによって、色々な対応が求められるようです。
個人として、どのような対策が必要か調べていくことも大事ですね!
認知行動療法講座

就労移行支援事業所リスタートでは、「ものの受け取り方(認知)」を変えることで「感情」やそれによる影響を抑える「認知行動療法」についての講座を毎週やっています。
前回まで、5つのコラムについて練習していましたが、今回はいよいよ、7つのコラムの説明に移ります。
残るコラムは、第6のコラム「適応的思考」と第7のコラム「心の変化」の2つです。
第6のコラム「適応的思考」
適応的思考とは、自動思考に代わる、柔軟で現実的な考えのことです。
5つのコラムまでで、マイナスの感情を呼び起こした元々の自動思考が、認知の歪みを含み、現実よりも悪く受け止めた結果であったことが見えてきたのではないかと思います。
そこで、第4のコラム「根拠」と第5のコラム「反証」で挙がった内容を元に、より現実的で、柔軟さのある考えを作っていきます。
適応的思考の最も簡単な作り方は、根拠の内容と反証の内容を、そのまま繋げてしまう、というものです。
そう考えるに至った理由となる事実と、認知の歪みなどから見えてきた事実とそぐわない部分の両方を受け入れることにより、元の自動思考よりも現実的な考えが生まれるはずです。
また、自分のこととなると厳しく考えてしまう場合もあるため、自分ではなく、親しい友人が同じ状態だったらどうアドバイスするか、という目線で考えてみるのも有効です。
第7のコラム「心の変化」
最後のコラムは、考え方を変えたことによる「心の変化」です。
元の自動思考から、新しく適応的思考に切り替えてみることで、第2のコラムで挙げた「気分・感情」にはどのような変化があるでしょうか。
もしも、まるで変化がないということであれば、再び第3のコラムまで戻り、自動思考とその根拠、反証を探しなおしてみてください。
第2のコラムと比べ、マイナスの気分が減少し、落ち着いていたならば、コラム法は成功と言えるでしょう。
ここで重要なのは、0%を目指すことではありません。
考え方を変えるだけでは、マイナスの気分、感情が完全になくなることはありません。
ネガティブな気持ちを落ち着け、これから先、「行動」を起こしやすくすることが、コラム法の目的です。
就活対策「PREP法/電話対応~取り次ぎ~」

リスタートの就活対策講座は、ビジネスマナーについてただ講義を聞く形式ではなく、実践をすることで訓練をしています!
今日のテーマは、「PREP法/電話対応~取り次ぎ~」についてです。
PREP法
リスタートでは、PREP法という方法を使ってプレゼンテーションをする練習を行っています。
PREP法とは、簡潔に要点を伝えるために理由や実例を交えて、伝える方法です。
①Point(要点、主張)
先に要点、主張を言います。
例)私はサッカーが好きです。
②Reason(理由)
要点や主張の理由を述べます。
例)サッカーは、世界で一番普及しているスポーツであり、足を使うことで偶発性がとても高く、スリリングな展開になることが多いからです。
③Example(実例)
実際に経験した例や事実を伝えます。
例)私は年に数回スタジアムに行き、スリリングな展開や臨場感を味わっていて、思っていないような展開を何回も体験しました。
そこでサッカーの展開や流れがいかに興奮するものかを感じています。
④Point(要点)
最後に、再度要点を伝えて締めます。
例)よって、私はサッカーが好きです。
上記の例は「好きなスポーツは?」というお題の例です。
①~④の順で説明をすることで、相手を説得させる・納得させる技術がついていきます。
定期的に行っていきますので、是非練習継続していきましょう。
電話対応~取り次ぎ~
先週から引き続き、電話対応の取り次ぎ方の続きを行いました。
実際に会社から電話がかかってきた時の実践です。
下記の点に気を付けて行いました。
①会社名や名前、連絡先などを復唱する
②元気よく対応する
③自分から用件を聞く
今回も、担当者が不在の場面についての対応を繰り返し練習しました。
皆さん昨週からの訓練で、徐々に上達してきている部分が多いです。
電話の取り次ぎは「慣れ」の部分も多いので、何回も練習して、より良い電話対応になるように意識していきましょう。