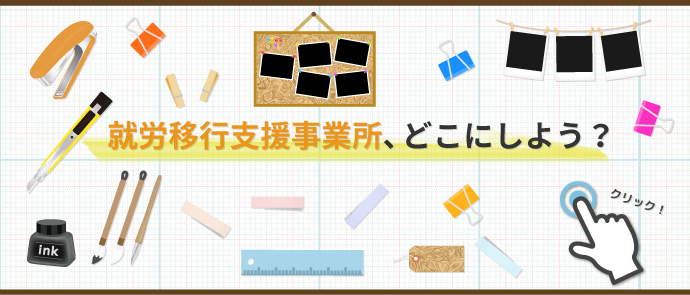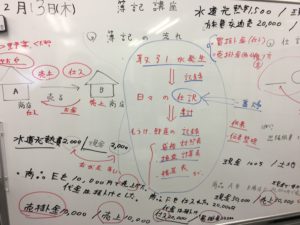受け取り方も伝え方も人それぞれ! 正確な情報共有のために必要なこと
散らかっている? 散らかっていない?
捉え方、人それぞれだね・・・
- 情報共有にミスがある!
- 情報共有、よく誤解がある
- どうしてうまく伝わらないの?
- 「こんなの聞いてない」と思うことがよくある

捉え方が違えば、対処方法も違う
同じ状況を見ても、リス太君は「散らかっている」と見えています。
K君には「そこまで散らかっていない」と見えたようですね。
このように、同じ状況でも、人それぞれ見方・捉え方、考え方が違うものです。
ひとつの仕事でも「これならできそう」と捉えるか、「自分には無理だ」と捉えるかは異なりますね。
知識、経験、スキルはもちろん、性格もあるでしょう。
しかし、捉え方が違うということを念頭において報連相をしないと、誤解やトラブルになってしまいます。
捉え方が違うため、このように報連相にも違いが出てくることも。
重要な情報では、この相違でトラブルになってしまう、ということは防がなくてはいけません。
相手を信用していない、というわけではありませんが、抽象的な表現ではこういった部分でトラブルになってしまうことがあるのです。
相違や誤解を防ぐ
どういう状況を、どう捉えているのか、というのは、具体的な数字がないと正確に共有できません。
とくに大切な情報では、具体性が必要になってきます。
伝える側なのであれば、具体的な数字を伝えるようにします。
どのくらいの部屋が、どの程度散らかっているのかは、受け取る側はそれだけではイメージができません。
抽象的な表現だけではなく、相手がイメージしやすい言葉を使います。
そして最後に「○○という対応でよろしいでしょうか」と述べるようにします。
受け取った側との考えの相違がある場合は「それではダメだ」と言われてしまいますが、そこを起点に、正しく共有が進んでいくでしょう。
もちろん相違がなくきちんと伝えられていれば「いいだろう」と判断ができるでしょう。
また、受け取る側も、受け取った言葉そのままでは不足があるかもしれません。
床に散乱しているのか、順番が整理されていないだけなのか、といった情報を聞き取れるよう質問します。
報告に「○○したほうがよい」という提案も含まれていた場合、その根拠も問うとよいでしょう。
こちらも、相手の性格、普段の言葉の使い方を考えてみると、より具体性が増します。
例えば、相手が「いいね」と肯定的にとらえる性格であった場合、その人の「よくない」という判断はかなり重度であると考えられます。
ほかにも口癖、しぐさ、態度などもヒントになるでしょう。
相手が伝えようとしている情報を、できるだけ正確につかむために、受け取る側も工夫が必要です。