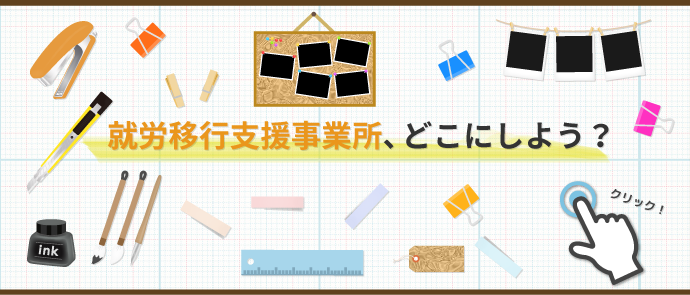コミュニケーション「5人のツアーガイド」認知行動療法講座「7つのコラム」
新聞読解「次は『働きがい改革』」

以下、記事の要約です。
働きがいを意味する「エンゲージメント」を重視する日本企業が増えている。組織の「健康診断」を実施して職場風土を改善し、生産性アップや離職防止につなげる狙いだ。
単なる働き方改革だけでは、労働意欲を高めにくい。経団連が旗を振り、三井住友銀行が意識調査を始める。働きがい改革は、日本企業が競争力を取り戻す妙薬になるか。
この記事に対する利用者さんの意見・感想
- エンゲージメントを上げることで生産性が上がればいいなと思った。
- 早期離職を減らす働きがい改革は良いことだと感じた。
- 毎月調査することは良いと思う。
- 社員の意識を上げるためにどう工夫するかも大切だと感じた。
残業時間などの働き方改革だけでなく、やる気や生産性を上げる働きがい改革も今後注目されていきそうですね!
認知行動療法講座

就労移行支援事業所リスタートでは、「ものの受け取り方(認知)」を変えることで「感情」やそれによる影響を抑える「認知行動療法」についての講座を毎週やっています。
前回は、サンプルを用いて5つのコラムの実践をしました。
今回は、第6、第7のコラムを紹介していきます。
7つのコラム
第4のコラム「根拠」と第5のコラム「反証」を基に、新しい考えを探していきましょう。
第6のコラム:適応的思考
適応的思考とは、自動思考に代わる新しい考えとなる、柔軟で現実的な考え方のことです。
適応的思考は、以下のようにして作ります。
・第4のコラムで挙げた根拠が自動思考と完全に矛盾している場合には、その根拠に基づいた新しい見方を考える。
・根拠と反証がどちらも部分的に自動思考を裏付ける場合には、双方を含んだバランスの良い見方を考える。
・元の自動思考が当たっていたとして、最悪の可能性と最善の可能性を考え、その中間となる現実的な可能性を考える。
・自分の信頼する人が同じ状況にあったとしたらどんな考え方をするか想像してみる。
・親しい人が同じ状況で同じように考えていたとしたら、なんと声をかけるか想像してみる。
第7のコラム:心の変化
最後の第7のコラムには、考え方を変えてみて感情や気持ちがどのように変化したかを書き込みます。
そこで気持ちが楽になっていれば新しい考え方が役に立ったということがわかり、そうした考え方をまたこれからもしていけばよいということになりますし、あまり変化が見られない場合には、また別の考え方や見方ができないかと考えてみることができます。
これによって、ストレスに押しつぶされない柔軟なものの考え方が見つけられるようになるはずです。
コミュニケーションプログラム
リスタートでは、毎週火曜日にコミュニケーションのプログラムをやっています!
言葉の通り、プログラム内で利用者同士コミュニケーションを図ることを目的としたプログラムです。
どんな職場で働くにせよ、多かれ少なかれ必要となるコミュニケーションの能力ですが、一口にコミュニケーションと言ってもその意味するところは多々あります。
プログラム内では、主として以下の能力を磨くことを目標としています。
・言葉以外のコミュニケーションによる情報を受け取る
・グループの一員として協力し、目的を達成する
・自分の言動を周囲がどのように受け止めているかを知る
・情報を誤解なく伝える方法を身に着ける
・自分の希望や意見を相手に伝える
第十三回となる今日は、「5人のツアーガイド」というワークをやりました!
5人のツアーガイド

今回のワークは、以前のNASAゲームに近いコンセンサスのためのワークです。
ワークの内容は、ボランティアでついてもらうツアーガイドを、5人の中から選ぶというものです。
これらのツアーガイドには、「知識が豊富」だが「押しつけがましい」など、それぞれいいところと悪いところがあります。
グループでお願いするツアーガイドを決めるために、自分の意思をはっきりと告げて、お互いに納得することを目標として話し合いをしました。
今回参加した利用者さんからは、以下の振り返りがありました!
- 他の人の意見を聞く中で、自然と納得し自分の意見も変化していった。
- 人によって想像するものは異なるので、具体的なイメージを共有することが大切だと思った。
- 例のおかげで理解しやすくなると、納得感に繋がると感じた。
- 意見を変えるときなど、どのように感じてどのように変わるのかハッキリと表明することの重要さに気づいた。