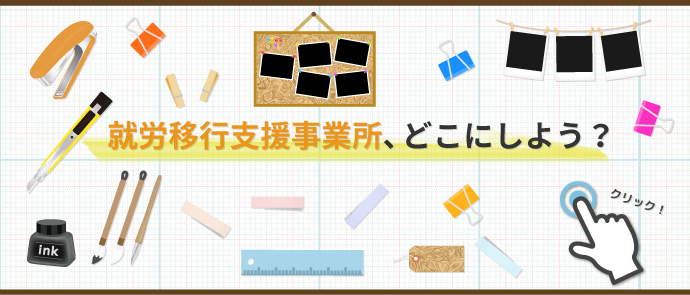就活SST「新たな選択肢を生む”創造性”」
新聞読解「「道の駅」始まりはトイレ」

以下、記事の要約です。
「道の駅」制度発足から来年で30年。今や年間延べ2億人以上が利用し、道の駅自体が目的地にもなっている。
道の駅の制度創設に尽力した大石さんは「役人ではなく民間のアイデアから生まれた」と振り返る。
きっかけは、ある人物の一言だったと言う。
このテーマについての利用者さんの意見
- 1200か所も道の駅があるなんて驚いた
- 地方活性には必要不可欠
- 特産物など興味がある
- 観光スポットとして楽しみの一つ
今後も存在価値をアピールしていって欲しいですね!
就活SST

前回は、変えられるものは未来と自分で、過去と他人は変えられないという話をしました。
今回は、上質世界に含まれるものを手に入れるために発揮される”創造性”についてのお話です。
新たな選択肢を生む”創造性”
創造性とは、欲求を満たすために新しいものを生み出すことです。
例を挙げるなら、「いつでもどこでも音楽を聴きたい」という欲求を満たすために携帯音楽プレーヤーが発明された、というのも創造性によるものであると言えるでしょう。
しかし、創造するものは物理的なモノだけではありません。
欲求を満たそうとして、最善であると考えていた行動がうまくいかなかったとき、次の選択肢を見つける働きも創造性によるものです。
例えば、いつも乗っている電車がトラブルで動かなくなってしまっていたとき、「他のルートを探そう」とか、「一度会社に連絡しよう」と考えるのは、創造性が働いている状態であると言えるでしょう。
一方で、「会社でミスをしてしまったため、翌日会社を休む」とか、「嫌なことがあったので、暴飲暴食で晴らそうとする」というのも創造性の働きです。
創造性によって選ばれる選択肢は、”自身にとって”最適であると考えるものです。
そのため、周囲から見て不適切な選択であったとしても、過去の経験からそれが最も良い方法だと判断していれば選んでしまうのです。
創造性がマイナスに発揮されるのを防ぐためには、普段から情報を集め、選択肢を広く持っておくことが大切です。